










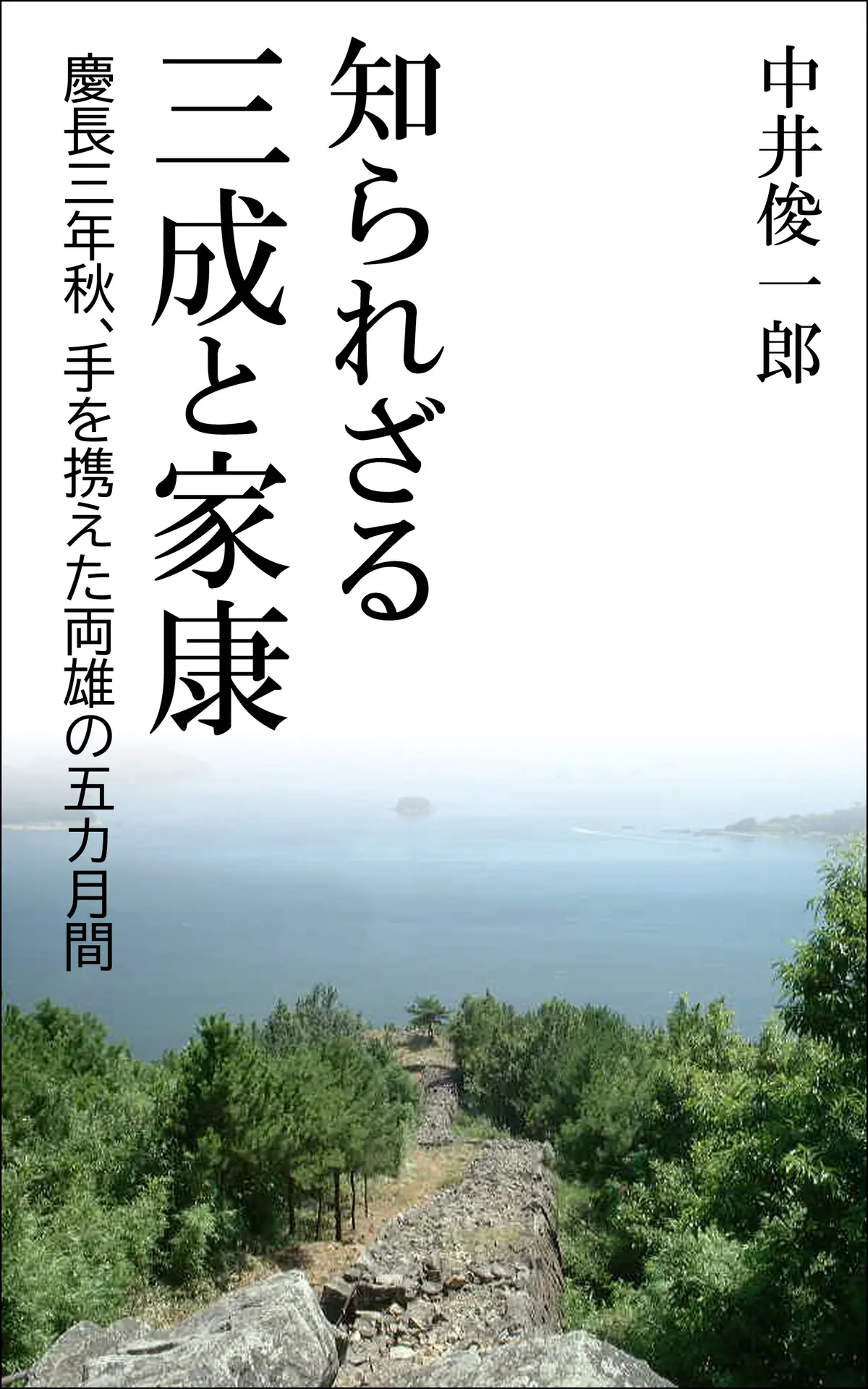
石田三成と徳川家康が手を携えて、ともに日本の危機を救った、と言ったら皆さんはどう思われるだろうか。少しでも日本史を知っている人なら、あり得ない話と冷笑されるかも知れない。改めて言うまでもなく、慶長五年(一六〇〇年)三成と家康が関ヶ原で戦い、勝者となった家康が三成を処刑したことは、多くの史料に描かれた紛れもない史実である。しかし人生の最期に敵対する立場にいたからといって、その二人がずっと仇敵のような間柄だったというのは、あまりに短絡的な発想ではないだろうか。三成は家康を敵対視していた、秀吉死去のすぐ後に、三成は家康を暗殺しようとしたという類の話は多い。しかし出典を辿っていくと、ほとんどが根拠のない後世に作られた話であることが分かる。同時代の一次史料から見ると、三成と家康は、終始対立関係にあったということは出来ない。それどころか逆に両雄は協力関係にある期間が長かった。特に協力関係にあったと言えるのは秀吉の死後数ヶ月間である。本書では、その間の両雄の行動を、一次史料の分析を中心に時系列的に考察してみた。その頃、日本は大きな危機に見舞われていた。当時、三成と家康は、秀吉が始めた朝鮮出兵、文禄・慶長の役を如何にして終わらせるかに苦慮していたのである。史書の多くは朝鮮出兵の終わり方について、「秀吉の死後、戦いに疲れた日本側は引き上げた」などと簡潔に記している。しかし、当時朝鮮にいた七万の日本勢は深刻な危機に瀕していた。秀吉の死は深く秘匿された筈だったが、この情報はすぐに敵国、明・朝鮮側にも知られることとなった。復讐心と憎悪に満ち、嵩にかかって攻め寄せようとする朝鮮民衆と明軍の反転攻勢に曝され、司令塔と戦争目的を失った現地の日本勢は孤立していた。諸将の思惑も交錯し、政権の求心力は低下していた。秀吉の死により、強制的にこの危機解決に直面させられたのが、三成と家康たちだった。三成も家康も、秀吉の朝鮮出兵には、批判的ないしは傍観的であった。その二人が最後に、この戦役に幕を下ろす役目を割り振られる事となった。戦争は、始めるよりも終わらせるのが難しいと良く言われる。当たり前のことであるが、一方の都合だけで終えられるものではない。独裁者が死んで戦争を終えたいと一方が願っても、相手側はそうおいそれとは応じてこない。秀吉が死んだ慶長三年八月から、日本勢の殿軍を務めた島津勢が博多に引き上げてくる十二月までの約五ヶ月間、三成と家康は協力してこの困難な状況を担い、大きな損害なく撤兵を実現させた。だが当時の情勢を追っていくと、それは正に紙一重の状態であったことが分かる。現在の世界情勢もまた戦乱の中で混迷を極めている。この情勢下で、かつての日本の対外出兵がどう終えられたのか、そこで何が起きていたかを考えるのは、意味があることではないだろうか。そしてその中で、三成と家康という二人の対照的な人物がどのように協力し、危機を乗り越えたかを見ていきたい。続きを読む
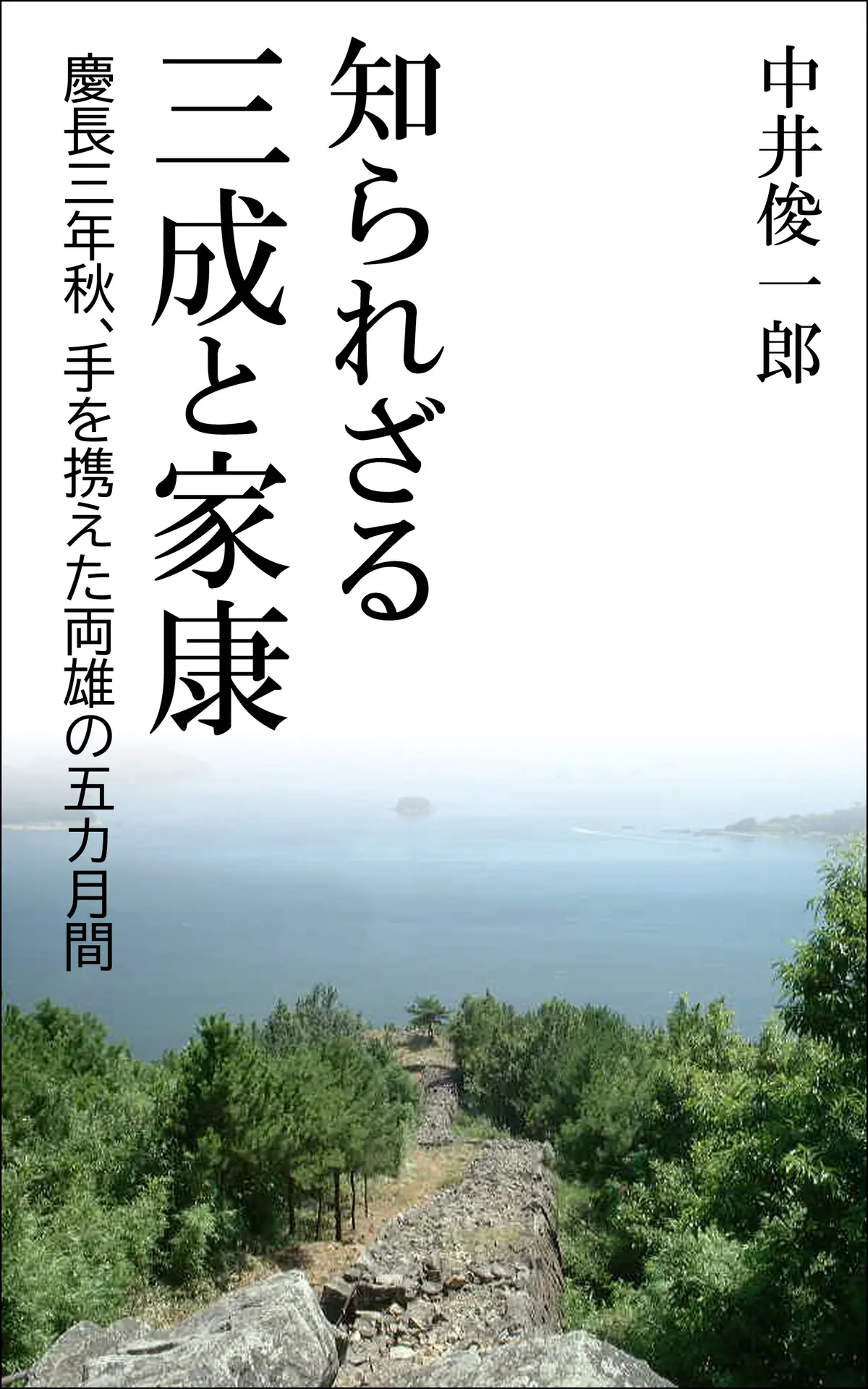
知られざる三成と家康: 慶長三年秋、手を携えた両雄の五カ月間
- ASIN :B0CHLC1XHC
- 出版社 :Independently published (2023/9/7)
- 発売日 :2023/9/7
- 言語 :日本語
- ペーパーバック :83ページ
- ISBN-13 :979-8859199297
- 寸法 :14.81 x 0.48 x 21.01 cm